
THE BEACH BOYS
FOLLOWERS

そもそもBeatlesやRoling StonesやBeach Boysの影響を全く受けていないロックバンドなんてあり得ないのだが、そんな中でも特にBeach Boysのヴァイブレーションを感させるミュージシャンをピックアップしてご紹介したい。
パッと見ておわかりいただけると思うが、このページのチョイスはかなり偏っているので鵜呑みにしないほうがいいでしょう。古き良きアメリカの青春を体現するエンタテイナーであり、高度な音楽性を誇るクリエイターであり、限りなくスピリチュアルなオーラを放つBeach Boys、その全てを再現するなんて所詮無理な話なのだ。一般にフォロワーと言われているミュージシャンは、Beach Boysの美しいハーモニーや屈託のないキャラクターをトレースしている人が多い。逆にいえば、それ以外の面ではBeach Boysに遠く及ばないわけだ。それと同じことで、Brianの音像へのこだわりに敬意を表した音楽や、内向性に共鳴した音楽があってもいい。

The High Llamas

元MicrodisneyのSean O'Haranが結成した奇妙なポップバンド。Van Dyke Parksばりのストリングスに包まれたアルバム「Gideon Gaye」で注目を集めて、続く「Hawaii」では「SMiLE」のサウンドに挑戦してみせた。音響派への接近を経て、1999年にはナチュラルなポップアルバム「Snowbug」を発表。音像はあくまで深く、でもフレンドリーな心地よさと優しい手触りを感じさせる名盤だ。
Beach Boysマニアの間では、彼らを認めるか否かでずいぶんと意見が別れているが、当のBrianは「逆に僕の方が彼らの影響を受けているんだ」とも語っている。彼がHigh Llamasに本当に感銘を受けたのか、熱心なフォロワーへのただのリップサービスなのかは疑問が残る。

Jim O'rourke

ポストロックの鍵を握る一人。そもそも現代音楽の世界でギターの即興演奏をしていたが、StereolabやHigh Llamasとの共演でポップミュージックに接近、99年には初めて歌モノのアルバム「Eureka」を発表した。ミニマルなアコースティックギターと透明なピアノが生み出す不思議な音風景の中を、Jim自身の線の細いボーカルがゆるやかに漂う世紀の大傑作だ。
Brianはポップソングの世界からあの驚異の音響に辿り着いたわけだが、逆の視点から同じ目標を見つめているのがJimではないか。Jimの音楽は、ポップスというフォーマットを借りて、音の粒ひとつひとつが持つ輝きを目に見える形に構築していく。Jim自身ももちろんBrianを強く意識していて、Beach Boysの曲をベースに壮大なミニマルミュージックを作る計画がある。

Wondermints

フォロワーというより、今やBrianの大事なパートナーになってしまったWondermintsだが、ここで紹介しておく。
そもそもパワーポップシーンの隅っこで地道に活動していた彼らが注目を集めたのは、Brianへのトリビュートライブ出演がきっかけ。デビューアルバムは日本のみのリリースだったものの、映画「AUSTIN POWERS」への出演でようやく本国でも認知された。現在はBrian Bandの中核としてツアーやレコーディングに参加している。
彼らの音楽性はBeach Boysに留まらず、WhoやSyd Barrett、ByrdsやKinksといった60年代のポップミュージックをごちゃ混ぜにしたもの。これまでに、BrianがGlen Campbellに提供した「Guess I'm Dumb」をカバーしているほか、メンバーのDarian SahanajaがソロでBrianの未発表曲「Do You Have Any Regrets」を、Nick Waluskoが「I Just Wasn't Made For These Times」をリリースしている。

Linus Of Holywood
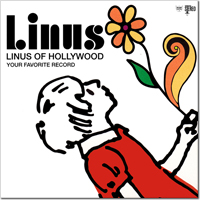
日本のソフトロックファンの間にあっという間に浸透した平成のYellow Balloon。実体はKevin Dotsonのソロプロジェクトだ。
パワーポップバンド、Size 14でデビューしたKevinだが、ルックスの良さが災いしてか、アイドル路線の中途半端なディレクションでパッとせずに解散。彼らのアルバムには、かのDaryl Dragonがゲスト参加している。その後、Puff DaddyやSmashing Pumpkinsとの仕事を経て、ついに自身のレーベルで思い通りに作り上げたのがLinus Of Holywood名義のアルバムだ。
デビューアルバム「YOUR FAVORITE RECORD」には、65年から67年頃のBeach Boysサウンドが満載。宅録とは思えない生き生きしたバックトラックにまずびっくり、Jeffrey Foskettもかくやのコーラスワークにまたびっくり。甘いメロディが次から次へと飛び出してシュワシュワとろけちゃう。ソフトロック界伝説のSSW、Margo Guryanがゲスト参加しているのも見逃せないところ。
 The Explorers Club

90年代のフォロワーは、ポストロック、あるいは音響派の文脈でBeach Boysをとらえなおそうという傾向にあったが、00年代のバンドは60年代のサウンドをそのままオリジナルに取り入れてしまう傾向にあるように思う。その代表格がこのThe Explorers Clubだ。
ジャケットには丁寧にも、盤が擦れて出来た傷の意匠までデザインされていて、そのマニアっぷりに期待が高まるが、内容を聴いてますます納得。Beach Boys、Phil Spector、Byrds、Beatles、Roger Nicols、60年代の雰囲気がまんま21世紀のリアルな演奏として聴けちゃう。楽曲のクオリティも極めて高い。特に曲名やコーラスアレンジにBeach Boysへの偏愛ぶりが見受けられる。

The Sonic Executive Sessions

Jellyfishのトリビュートアルバムでデビューを果たし、注目を集めたのがイギリスウェールズのThe Sonic Executive Sessions。といってもJellyfish的な下世話さはなくて、Beach Boysへの愛情をSteely Dan的な完璧な演奏で表現している。
特筆すべきは美しすぎるソングライティング。サウンドがSSWだったりパワーポップだったりソフトロックだったりジャズだったりしても、楽曲の良さにぶれがない。そして最後の魔法はBeach Boys風のコーラスワーク。Linus Of Holywood、The Explorers Clubと並んで2010年代のBeach Boys業界を牽引することになるだろう。

Louis Philippe
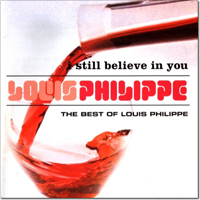
el Labelの看板アーティスト。イギリスで活動して日本で売れた、アメリカンポップス好きのフランス人。そもそもBorder Boysという名前で活動していたあたりからもフリークぶりが伺えるが、ソロに転向してからは「Pet Sounds」〜「Friends」風の内省ポップスに傾倒している。96年発表のベストアルバムにはビーチ・ボーイズナンバーが3曲も収められていてお薦め。
el Label出身らしく、予算のなさを逆手にとった独特のサウンドは、Elephant 6系にも通じる手触り。アメリカンな甘いメロディとヨーロッパの翳りのブレンドも見事で、お日様の下で微睡むような肌に柔らかい名曲が揃っている。ハーモニーのクオリティは山下達郎先生のお墨付き。老若問わずどなたにでも楽しめる。

Jeff Larson

2000年頃から活動を開始、ウェストコーストサウンドを爽やかに蘇らせたアメリカのシンガーソングライター。クラシックなカリフォルニアサウンドは、Beach Boysファンにも親しみやすいはず。
Jeffrey Foskettと交流が深く、ボーカルアレンジャーとして多数のアルバムに参加している。また、Timothy B. SchmitやRobert LammなどBeach Boysと関わりの深いミュージシャンも多数客演している。

BMX Bandits

アコースティックギターをかき鳴らし、ナチュラルで躍動感溢れるポップスを聴かせるスコットランドのユニット。デビュー当時はラウドなロックバンドだったが、Creation Recordsに移籍した頃から60年代ポップス趣味を爆発させた。グラスゴー周辺のポップシーンを束ねるスーパーバンド的な存在で、Teenage FanclubやPastelsの中心メンバーも掛け持ちで参加している。
リーダーのDuglas T Stewartは、グラスゴーでも一番のBeach Boysコレクター。娘の名前はRhondaさん。カバーする曲もマニアックで、これまでに「Darlin'」のプロトタイプの「Thinkin' 'Bout You Baby」や、Brianのソロ「Love And Mercy」を取りあげている。Beach Boysマニアにお薦めしたいのは95年の「Gettin' Dirty」。ギターが引っ込んだソフトロック的なアプローチで、Beach Boysスタイルのコーラスも顔を出す。なぜか日本の童謡「春の小川」をカバーして、「Let's Go Away For Awhile」を思わせる美しいインストに仕上げている。

Elvis Costello

パンク、ギターポップからBurt Bacharachとの共演アルバムまで、幅広い振れ幅で活躍しているElvis Colsetello。彼もまたBeach Boysの信奉者で、特に「Cuddle Up」の素晴らしさについて何度も言及している。
カラカラの声質がBeach Boysのカバーに向いてないと判断したのか、自身のアルバムではBeach Boysのカバーは披露してないが、ライヴで「God Only Knows」を歌ったことがある。また、2001年のElvis Costello with Anne Sofie Von Otter名義のアルバムでは、「Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)」と「You Still Believe In Me」を丁寧にカバーしている。

XTC

ニューウェイヴバンドとしてデビューし、独特のコードセンスで注目を集めたXTC。メンバーの脱退やリーダーAndy Partridgeのステージフライトでレコーディングバンドになってからは、60年代のポップサウンドを積極的に取り入れるようになった。特にThe Dukes of Stratospher名義で発表した音源は60年代の幻のバンドのものと噂された。
Dukes名義の「Pale and Precious」は「Pet Sounds」「SMiLE」期のBeach Boysへの完璧なオマージュ。続くXTC名義の名盤「Oranges & Lemmons」では「Surf's Up」を思わせるバラード「Chalkhills and Children」を披露している。

She & Him

女優Zooey Deschanelと、プロデューサーでシンガーソングライターM.Wardのデュオ。Zooeyの趣味で、60年代のアメリカンポップスの手触りを今のポップスに昇華している。アルバム「A Very She & Him Christmas」で「Christmas Day」をカバーしているほか、ライブで「God Only Knows」などBeach Boysナンバーを多数取り上げている。
2015年には2人でBrianのソロアルバムに参加した。

The Flaming Lips

80年代から活動するアメリカのオルタナティブロックバンド。数々の実験的な取り組みの末に音響派に接近したアルバム「The soft bulletin」でブレーク、同時に60年代のロック・ポップスへの愛情を露わにした。
ライブのBGMにしばしばBeach Boysのアルバムを使用、2012年にはMOJO誌のトリビュート企画で「Go
d Only Knows」を、2015年にはBrianのトリビュートライブで「Good Vibrations」を大胆にカバーした。

Tame Impala

オーストラリアのサイケロックバンド。2012年のアルバム「Lonerism」がグラミー賞オルタナティブアルバムにノミネートされたり、NMEの年間ベストアルバム1位に選出されて大ブレークした。60年代後半のサイケデリックな感触をストレートに再現。
ソングライティング・プロデュースを担当するKavin Parkerのお父さんは、かつてBeach Boysのカバーバンドで演奏し、Kavin自身も新世代のBrian Wilsonと称されている。

Primal Scream

Bobby GillespieとJim Beattieの双頭バンドとしてデビューしたPrimal Scream。脱退したJim Beattieがその後Spirea XやAdventures In StereoとしてBeach Boys趣味を爆発させたのは前述の通り。
Bobby Gillespieが残ったPrimal Screamはアルバムごとにサウンドを変え、モンスターバンドとして現在に至るが、2015年にBobbyのお気に入りを集めたコンピレーション「Sunday Mornin' Comin' Down」には「'Til I Dile (Alternate Mix) 」「Forever (A Capella Mix)」「You're Welcome」と3曲ものBeach Boysナンバーが収録された。

June & The Exit Wounds
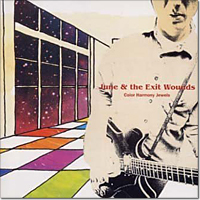
読み難いバンド名からして聴く人をよせつけないムードが漂うが、実にハートウォーミングなポップスを聴かせてくれる注目のユニット。日本ではLinus of Holywoodと同じPhilter Recordからリリースされている。
サウンドは往年のA&Mを思わせる、ピアノがリズムを刻む柔らかな手触り。鼻にかかった少年声、人なつっこいファルセットヴォイスは女の子に受けそうだが、歌詞をみると「駄目な僕」系で男の子も胸キュン。60年代のポップソングを、Todd Rundgrenを触媒にして現代に蘇らせたようなメロディセンスが素晴らしい。ストレートにBeach Boysを連想させる曲は少ないものの、彼ら絶対嫌いじゃないはず、と踏んでいたらやってくれました、「All I Wanna Do」のカヴァー。

Papas Fritas
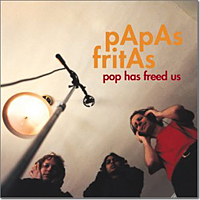
Minty fresh Labelの男女混声ポップバンド。Wondermintsにも通じるインドアバブルガムサウンドだが、貧乏を逆手にとって可愛い手作りポップスに昇華するセンスを持ち合わせていて、アルバムとしてはこっちの方が断然おもしろい。癖のない女性ボーカルと、70年頃のDennisを思わせるしゃがれた男性ボーカルのミスマッチ感も最高だ。
叫ぶより楽しむ方がポジティブだし、ポップソングはそのために使い捨てられちゃってもいいというのが彼らの持論だそうで、でも「Brian Wlisonの曲のように本当に優れたポップミュージックは永遠に飽きないから残りつづけるのさ」とも。フレンドリーでいかにも日本人向けな感じではあるが、本国ではBlurやCardigans、Flaming Lipsなどのフロントアクトをつとめ、CMJチャートでも1位をゲットした。

Matthew Sweet

90年代を飾ったギターポップ、パワーポップ勢は、多かれ少なかれBeach Boysの影を感じさせる。例えサウンドが違ってもだ。甘酸っぱいポップソングを奏で、アルバム「GIRL FRIEND」で一世を風靡したMatthew Sweetもその一人。同志とも言えるVelvet Ctushには「TEENAGE SYMPHONIES TO GOD」なんてアルバムもある。
Matthew Sweet Susanna Hoffs名義のアルバム「under THE COVERS VOL.1」では「The Warmth Of The Sun」をカバー。美しく誠実な演奏だ。また、アルバム「Living Things」にはVan Dyke Parksを招いている。

Le Super Homard
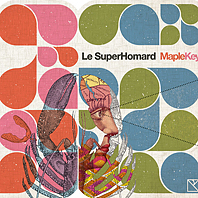
90年代からThe Strawberry Smellのメンバーとして活動、エンジニア・プロデューサーとしても評価の高いフランスのミュージシャン、Christophe Vaillantのソロプロジェクト。
60年代、70年代のポップソングを始め、90年代にBeach Boysを再解釈したStereolabやHigh Llamasの影響を強く受けたサウンドを展開している。90年代のフォロワーたちよりは原典に近いフレンドリーな感触。

Jellyfish

Andy Sturmer、Roger Joseph Manning Jr.、Jason Falknerらが参加していたサンフランシスコのパワーポップバンド。本国よりイギリスで高く評価された。
その派手に装飾されたサウンドはQueenやBeatlesやXTCに喩えられたが、むしろ彼らが影響を受けたBeach Boysのコーラスワークとコード感に支えられている。特にファーストアルバム「BELLYBUTTON」の名バラード「Calling Sarah」や、セカンドアルバム「SPILT MiLK」のリードトラック「Hush」は、Beach Boysのコーラスワークやサウンドを再現して話題を呼んだ。

Paul Steel

21世紀のJellyfishは彼かも知れない、イングランドのPaul Steel。同じBeach BoysマニアであるAndy Partridgeや、Van Dyke Parksからも手放しの賞賛を浴びる若きパワーポップSSWだ。
Jellyfishなみにポップで濃密、カラフルでサイケデリックに弾けるサウンドを、Beach Boys風のコーラスワークでまとめあげる。特に美しいバラード「Summer Song」は「Let's Go Away A While」を思わせる浮遊感のある白昼夢のようなコード感、アルバムタイトル曲「Moon Rock」は「Wouldn't It Be Nice」だろうか。押しの強い声質は好みがわかれるところ。

POP ETC (The Morning Benders)

Elephant 6系のアマチュアリズム溢れるポストロックを、アコースティックサウンドで再構築するカリフォルニアのバンド。リリースはイギリスのRough Tradeから、といえば彼らの方向性がわかるだろうか。
The Morning Benders名義のアルバム「BIG ECHO」から、リードトラック「Excuses」は大勢のミュージシャンやシンガーが集まって一発録りするWrecking Crewのスタイル。同じ楽器をいくつも重ねるサウンドはPhil Spector的でもありながら、コーラスのセンスはBeach Boysのもの。曲によっては初期Beach Boysの彷彿させるガレージ感もある。なによりもVo.GのChris Chuの繊細でいなたい佇まいがBrianの背中とかぶる。

Adventures In Stereo

Primal Screamがポップバンドだった頃の中心メンバー、Jim Beattieのソロプロジェクト。バンド名の意味するところは「モノラルへの回帰」だそうで、1960年代のポップスが持つ暖かさや青臭さを、現代のシニカルな視点から取り戻そうとする試みだ。
Jimがルーツに挙げるのはVelvet UndergroundとBeach Boys。特にBeach Boysへの偏愛ぶりは相当で、今のレーベルのオーナーが自分よりBeach Boysに詳しいことに衝撃を受けて契約を決めたというエピソードを持つ。音のほうは微笑ましい男女混声のサイケポップス。手触りは60年代末のBeach Boysに近いが、発想はVelvet的なぶっきらぼうさをみせる。

The Apples In Stereo

そのAdventuresと紛らわしいことで有名なのがApples In Stereo。音の方も紛らわしくて、やっぱり60年代末のBeach BoysとVelvet Undergroundを合わせたような、若々しくてセンチメンタルな演奏を聴かせてくれる。世捨て人っぽいAdventuresと比べると、Applesはアイデアがあふれて止まらない無邪気なこども。「Love You」のようにムーグがブリブリと跳ね回るインドアガレージポップスだ。シングル「LET'S GO!」で、「Heroes And Villains」をカバー。問題はSean Lennon系の弱々しい喉声を認められるかどうか。
特に無邪気度が高いのはアマチュア時代の音源を集めたMarbles名義のアルバム。あまりの宅録感は聴いてて恥ずかしくなるのだが、否定できない世界だ。彼らのプライベートスタジオは、その名もPet Sounds Studioという。

The Olivia Tremor Control

ApplesのRobert Schneiderを中心に結成されたインディーズレーベル、Elephant 6を代表するポップバンド。Elephant 6周辺のバンドはどれも、Brianが部屋にこもってからの内省的なポップセンスと、John Cageをはじめとする前衛音楽のエッセンスを融合したような、ハンドメイドなポップサウンドを持っている。この界隈のポストロックシーンはなべてBeach Boysの強い影響下にあると思っていいが、その中でもまっ先にお薦めしたいのが彼らだ。
飾りっ気がないことが美徳とされる世の中で、彼らの音楽は飾りっ気だけでできたロック。「SMiLE」の音遊びの楽しさを、おもちゃの楽器のセッションやミュージックコンクレート的な手法で蘇らせようというもの。メロディのセンスは中期Beatlesっぽかったりして、この手のバンドにしてはポップで聴きやすい。

Yo La Tengo

音楽ライターIra Kaplanとアニメ作家Georgia Hubleyのカップル、Dinasour JRを結成する前のJ Mascisとバンドを組んでいたJames McNewによるUSオルタナティブロックの重鎮バンド。80年代から活動して多くのフォロワーを生んだ。
初期の荒々しいサウンドからだんだんソフィスティケイトされて、近年はポップスファンの間でも非常に評価が高い。特にルーツロックをガレージ風に解釈したカバーは秀逸で、Beach Boysマニアにお薦めできたもんかわからないが、「Little Honda」や「Shut Down」のパワフルなカバーを披露している。

Young Gun Silver Fox

Mamas GunのフロントマンAndy Plattsと、Amy Winehouseなどに楽曲提供してきたプロデューサー・ソングライターのShawn Leeが2015年に結成したイギリスのユニット。
往年のウェストコーストサウンドを目指した乾いた切ないメロディと、Andyのソウルフルなボーカルがあいまってヒットを記録。Beach BoysやByrdsがAORの時代を生きたら、的な心地よさ。

Darkstar

ポスト・ダブステップを出自として、イギリスの大衆音楽史をエレクトロニックポップに昇華するユニット。音楽的にBeach Boysに近いとは言い難いものの、その美意識と音楽性はWarp RecordsのオーナーSteve Beckettに、「Beach Boys, Brian Eno, Radioheadが交差する場所に存在する」と絶賛された。
特にアルバム「News From Nowhere」の美しいハーモニーワークは、「Pet Sounds」の影響を受けたことをメンバーも認めている。

Bror Forsgren
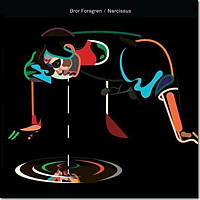
ノルウェーのエクスペリメンタルユニットJaga Jazzistのギタリスト。ソロアルバムではScott Walkerと共にBrian Wilsonへのリスペクトを公言、Brian Eno的なアンビエントとEnnio Morricone的な親しみやすいメロディを、緻密に積みあげたしたポップスの名盤となった。
特にソフトロック的なハーモニーと変幻自在な構成は、「SMiLE」期のBeach Boysとも重なる。

Sun Club

2015年にデビューしたアメリカのインディー・ポップバンド。The Beach BoysとAnimal Collectiveからの影響を公言して、やや脳天気なドリーム・ポップを展開している。
現状はメロディへのこだわりにBeach Boysに通じる美意識を感じる程度、今後彼らのBeach Boys性がどう形になるのか期待できそう。

Surfer Blood

フロリダ出身、2010年のデビューアルバムが各誌の年間ベストに選ばれたインディー・ロックバンド。
Gil Nortonをプロデューサーに迎え、Pixiesのフロントアクトを務めるなど、Beach Boysのイメージとは遠いが、「Don't Worry Baby」の秀逸なカバーを発表して驚かせた。

The Dukes Of Surf

ハワイのBeach Boysの異名を取るパロディーバンド。50'sから60's前半のサウンドとコーラスワークにハワイアンの味付けをして、脳天気を装っていた初期のBeach Boysを思わせるサウンドを脳天気に再現、中高年に人気を集めている。


The Beatles

フォロワーと呼んでしまうのはあまりに乱暴だが一応。1964年から67年頃まで、BeatlesとBeach Boysは大西洋を隔ててお互いの音楽性を刺激しあい、結果としてロックの可能性を飛躍的に拡大させた。
中でもベーシストでソングライターのBrianとPaulは、誕生日が2日しか違わないという因縁のライバル。Beach Boysへの明らかなオマージュ「Back In The U.S.S.R.」は言うに及ばず、この頃のPaulのソングライティングやベーススタイルにはBrianの強い影響が見られる。彼は最近のインタビューでも、オールタイムベストソングに「God Only Knows」、ベストアルバムに「Pet Sounds」を挙げていて、「Pet Sounds」がCD化された時にはロングインタビューを寄せている。
また、RingoとBrianは、今でもお互いのアルバムに参加しあうほど仲がいい。Sean Lennonもかなりのフリークで、ライヴで「In My Room」を演奏している。

Tony Rivers

イギリスで30年以上のキャリアを持つプロデューサー、セッションボーカリスト。60年代にはThe CastawaysやHarmony Grassのリーダーとして活動、Brian EpsteinやAndrew Oldhamが関わって大々的に売り出したもののさっぱり売れなかった。現在はプロデュース活動の傍ら、細々と宅録を続けている。
Castaways時代の演奏はビートバンド然としていていまいちだが、Harmony Grassは捨て曲なし。「TODAY!」期のBeach Boysサウンドにイギリスらしい影を落とした爽やかなハーモニーポップスだ。アコースティックギターには癖のないボーカルがよく似合う。70年代以降の作品もCDにまとまっていて、ますます透明度を増したハーモニーと、溌溂としたポップセンスが楽しめる。

Chris Rainbow
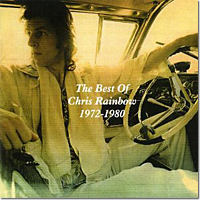
70年代に活躍したイギリスの宅録青年。シャイな性格も災いしてか商業的にはパッとせず、現在はAlan Parsons Projectに参加したり、地元でプロデュース活動をしている。70年代のイギリスのフォロワーはみんな不遇な星回りだ。
作品は、地味なキャリアから想像もつかないほど溌溂としていて楽しい。芯のあるBruce Johnstonというか、やんちゃな山下達郎というか。ちょっとプログレ臭くもあるクリアなサウンドと、独特のエフェクターをかけたサラサラしたボーカル。繊細で緻密に作り込まれたサウンドなのに、生き生きと表情のある声質のおかげで、解放感に溢れたフレッシュなポップソングになっている。Brianに捧げた深遠な「Dear Brian」や、「Sunflower」期のBeach Boysを思わせる楽しい「Ring Ring」は必聴。ポップスの鑑。

Jeffrey Foskett
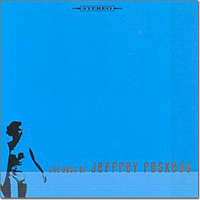
Beach Boysの周辺人物として、珍しくメンバー全員からの信頼を集めているシンガー。
70年代末に自身のバンド、Pranksを結成。ブリティッシュロックの影響を受けた力強いサウンドとウェストコーストらしいコーラスで人気を集めたものの、メンバーがそれぞれ別々のバンドに引き抜かれて空中分解してしまった。Jeffreyを引き抜いたのはほかならぬBeach Boysだ。81年から準メンバーとしてツアーやレコーディングに参加して、Brianのバンドで長年バンマスを努め、現在はMike-Bruce組に合流。
全盛期のBrianと比べると透明感は劣るものの、暖かみのある表情豊かなファルセットはさすが。音の方は、最近のBrianを思わせる中高音域が詰ったキラキラシンセ系だが、スリルもあって楽しめる。96年には日本のCM企画で「踊ろよフィッシュ」のカバーを小ヒットさせた。

The Sagittarius

Brianの作曲のパートナーだったGary Usher率いるSagittarius。ソフトロック史上の名バンドThe Milleniumの母体だ。当時リリースされたアルバムには未収録だが、幻のセカンドアルバム「THE BLUE MARBLE」で「In My Room」をカバーしている。
Gary UsherはBrianの曲を使って、何度かオーケストラアルバムを制作しているが、どれも原曲の爽快感がまるでなくて、安っぽいイージーリスニングに成り下がっているのが残念。

The Zombies

Beach Boysとほぼ同時期デビューのイギリスのロックバンド。1968年に発表されたセカンドアルバム「Odessey&Oracle」は、ソフトロックとサイケデリックを融合して、木管やメロトロンを導入した当時のBeach Boysに非常に近い手触りの傑作。アルバムからは「Time of The Season」のヒットも出ている。
バンドは間もなく解散するが、2000年代に再結成、新作のリリースやワールドツアーなど積極的に活動中。

First Class

Sagittariusへの曲提供でも知られるイギリスのプロデューサーJohn Carterが、名セッションボーカリストTony Burrowsらと結成した企画バンド。1974年にリリースした「Beach Baby」が全米4位の大ヒットを記録した。
ホーンやストリングスを取り入れた下世話で楽しいBeach Boys像を体現していて、BrianよりもCarlやWondermintsを思わせる。大ヒットした「Beach Baby」は「California Girls」系のワクワクするポップソングで、65年から66年のBeach Boysのエッセンスがふんだんに取り込まれている。アルバムの中にも地味な佳曲が隠れてる。キッチュで甘いメロディに浸りたい方にはお薦め。

Chris White
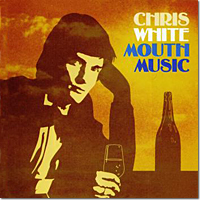
彼も70年代に活動したハーモニーポップのシンガーで、1976年には「Spanish Wine」をヒットさせたものの、ご多聞に漏れず表舞台から姿を消してしまった。現在はイギリスで趣味の宅録を続けながらBeach Boysファンクラブの運営に関わっている。
ちょっとハスキーな声質のせいか、70年代のBrianの枯れた味わいを思い出す。音数があるわりにはどこかスカスカしていて、ナチュラルで穏やかなツヤ消しのポップソングだ。突出した1曲はないものの、軽く聞き流すには気持ちいい。

Andrew Oldham Orchestra
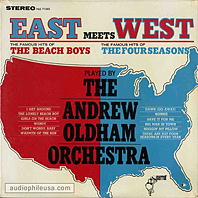
Brian Epsteinをサポートし、Phil Spectorに師事し、The Rolling StonesやSmall Facesの仕掛け人として名をはせたAndrew Oldham。イギリスにおけるBeach Boysの人気を確立した人物でもある。「Pet Sounds」に感動してBeah Boysを絶賛する広告を自腹で出し、イギリスでのBeach Boysの評価を決定づけたのは有名な話だ。
1964年のアルバム「East Meets West」では、Beach BoysとFour Seasonsの名曲をラウンジにアレンジして、LPの両面に納めた。

Billy Nicholls
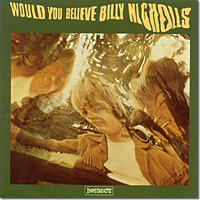
Pete Townshendとの長年にわたるコラボレイションや、Bob Dylan、Small Facesとの共演で知られるBilly Nicholls。彼が1967年に制作した幻のソロアルバムは、Andrew Oldhamが「Pet Sounds」への回答として用意したものだそうだ。Andrew Oldhamは上記の通り、当時のイギリス文化の最先端にいた人物。
アルバムはSmall Facesが参加していて、タフでサイケな仕上がり。ストリングスやパーカッションの使い方、ファルセットのコーラスにBeach Boysの影を見ることもできるが、Billy自身の音楽性にはBeach Boysの影響は感じられず、別物として楽しんだほうがよさそうだ。制作当時はリリースされず、伝説の名盤として一時はテストプレスが異様な高値で取り引きされていた。今はCDで2000円で買えちゃう。

John Cale
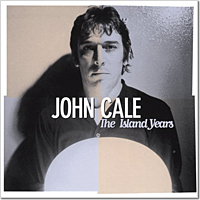
Beach Boysをオルタナティブな視点から評価した最初の人物。Velvet Undergroundの一員としてAndy Warholのパフォーマンスに参加して注目を集め、1967年にWarholのプロデュースでデビューした。Velvetがニューヨークのアートシーンの最先端にいた頃、我らがBeach Boysは時代遅れの田舎者だと思われていた。
75年の傑作ソロアルバム「Slow Dazzle」ではその名も「Mr.Wilson」という曲を発表。Brianはこの曲を聴いて自分への皮肉だと思ったそうだが、Caleは95年のドキュメントフィルムの中で、この歌の真意について、Brianの音楽の繊細さや純粋性について誠実に語っている。また「God Only Knows」のカバーを何度か試みているが、完成には至っていない。彼の場合、表面的なスタイルよりスピリット面での影響の方が大きいようだ。
Velvetはコマーシャルな成功はしなかったものの、今のロックにとってはミトコンドリアイヴみたいな存在。最近のBrianの再評価に、Caleの思い入れが少しは影響してるんじゃないだろうか。

Kraftwerk

テクノのルーツとして、現代の音楽に計り知れない影響を残したパイオニア。徹底したイメージコントロールをはかるため、自分達の思想や趣味趣向についてほとんど語ろうとしないが、あるインタビューの中でBeach Boysの「Once In My Life」というアルバムを絶賛している。これがどのアルバムのことを指しているのかは不明。ファンを惑わす罠なのか。
Beach Boysの影響が明確にあらわれているのは、彼らの出世作「Autobahn」だ。「Fun Fun Fun」を思わせる印象的なフレーズが繰り返され、ヴォコーダーを使ったいかにもBeach Boys風のコーラスパートに続く。パロディの部分は曲の本質とは関係ないが、あのキャッチーなコーラスがなければヒットはしなかっただろう。
細かいことをあげつらえばいろいろあるが、なによりBrian的なのは偏執狂的なスタジオ・ワーク、音響の快楽への貪欲なまでの取り組み方かも知れない。


細野晴臣

フォークロックの時代からエレクトロニカに至るまで常にコンテンポラリーなセンスを持ち続けて、自分より30歳も40歳も年下のミュージシャンに飄々と勝負を挑む怪人。彼がルーツに挙げるのは、ハリウッド映画のサウンドトラックとラジオから流れるBeach Boysだ。彼が初めて作った曲は「Surfin' JPN」という。
子供の頃はBeach Boysのポップスとしての新鮮さ、軽妙さに憧れていたそうで、彼らの音楽の懐の深さを痛感したのはアンビエントに接近していた90年代のこと。98年に森高千里との異色のコラボレーションで制作されたアルバム「今年の夏はモア★ベター」は、細野作品としては珍しく明らかなBeach Boysサウンドに仕上がった。
細野晴臣の場合、音楽そのものより佇まいや審美眼の中にBrianに通じるオーラがあるようで、彼のフォロワーには彼を凌ぐBeach Boysフリークが多い。Pizzicato Fiveは言うに及ばず、World StandardやTest Patternも要チェック。

Microstar
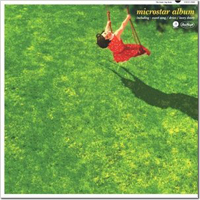
元Nice Musicの佐藤清喜率いるポップユニット。初期はテクノポップだったが、苦節数年の末に作り上げられたアルバム「microstar album」は、日本が世界に誇るべき王道ソフトロックの名盤になった。
最初は飯泉裕子の弾けきったボーカルがちょっと恥ずかしいかもしれないが、それを乗り越えれば至福のポップ体験が待っている。Duglas T Stewartがこんな文章を寄せている。「マイクロスターを聴くと、僕は、太陽の光が自分の顔に降り注ぐのを感じることができる。そして、キュートなチアガール達がレストランのプラスチックテーブルを囲んで、長い縞模様のストローでミルクシェーキを飲みながら、男の子のゴシップ話に夢中になっているところを、まるで本当に目の前にしているようだ。でも、マイクロスターの音楽は、他の時代の音楽のコピーなんかじゃない。彼らはその素敵なサウンドに、彼らにしかできない、ユニークで未来的なヒネリを加えているんだ。そのサウンドは、過去のものであり、現在のものであり、そして未来のものだ。さあ、マイクロスターを聴いて、君のその世界にも太陽の光を呼び込もう」

The Pen Friend Club

漫画家でもある平川雄一を中心としたガールズポップバンド。Beach Boysを徹底的にパロディー化したジャケットの1stでは「When I Grow Up (To Be A Man) 」「Darlin'」などをカバー、2ndでは「Guess I'm Dumb」「Please Let Me Wonder」などをカバーするなど、Beach Boysを中心とした60'sスタイルのサウンドで人気を集めている。平川雄一のオリジナルソングも往年の名曲に劣らない。
Jeffrey FoskettやThe Zombiesのフロントアクトを努めたり、平川はソフトロック系のデザインやライター業でも活躍の場を広げている。

黒沢健一
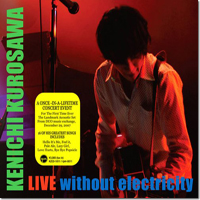
作曲家、プロデューサーとして、またL⇔Rのボーカリストとして一世を風靡した黒沢健一。L⇔R時代にもEquinox Labelを讃えたその名も「Equinox」という曲を発表している(作詞は牧村憲一)。萩原健太との趣味ユニット、健'Zでは「Melt Away」「I Just Wasn't Made For These Times」「Surf's Up」「Don't Talk」「Forever」をカバー。なんの趣味ってBeach Boys趣味ですよ。評論家と元ヒットバンドっていう肩書きを忘れて聴いてください。世界でもこのレベルはなかなかない。2008年に行われた「TOUR without electricity 2008」での「God Only Knows」は、鳥肌ものの名カバー。ライブアルバム「LIVE without electricity」で堪能できる。

Flipper's Guitar

イギリスのインディーレーベルから颯爽とデビュー、若さにまかせて目まぐるしく音楽性を変え、あっという間に消えていった伝説の2人組。はっぴいえんどから綿々と続いてきた日本人の洋楽観を解放して、そのかわり同世代のポップスファンには拭いきれない呪縛を残した。
Beach Boysの影響が見られるのはラストアルバム「Doctor Head's World Tower」。いかにも91年らしいマンチェスターサウンドの中を、昔のポップスの幻影たちが浮かんでは消えていく。自分が生まれる前の音楽が妙にリアルに聴こえる瞬間、古いポップスに今の胸の痛みを投影する自分の姿を描いた作品だ。アルバムの冒頭で「God Only Knows」のリフレインが顔をだし、「Heroes and Villains」のコーラスを経てBuffalo Springfieldにつなげている。また、10分34秒に及ぶ壮大なテーマ曲には、そこここに「Good Vibrations」が見え隠れしている。

Cornelius

元Flipper's Guitar、小山田圭吾のソロプロジェクト。デビュー当時はPaul Weller周辺へのオマージュが目立っていたが、やがてラウンジ〜ポストロックへの接近を見せて、次第にBrian的なスタジオ実験へと移行していった。特に97年のアルバム「FANTASMA」でのキュートで寂しい音像の快感は、限りなくBrianに近い。
彼の活動は海外でもよく知られていて、英MOJO誌のBrian Wilson特集では、R.E.M.のPeter BuckがBrianにCorneliusの音楽を紹介している。Brianはかなり興味を持っていたようだが、果たしてこのアルバムを聴いただろうか。写真上はPet Sounds SessionでのBrian、下はFANTASMA Sessionでの小山田圭吾である。こういうことをするから嫌われるのだ君は。

辻睦詞
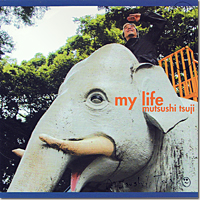
早すぎたポップトロニカバンド、詩人の血のボーカリストだった辻睦詞。Oh! Penelopeと名前を代えた頃から60年代ポップスの影響を正直に表現して、今はソロで活動中。趣味でBeach Boysの音源をマスタリングしたり「And Your Dream Comes True」や「God Only Knows」をカバーしたり、ライブでは「Melt Away」の素晴らしいカバーを披露した。現在Oh! Penelope時代の曲をアコースティックで再演するアルバムを製作中だそうで、その中にもBeach Boysのオマージュが出てきそう。

Pizzicato Five

ポップスに留まらず、ジャズやテクノ、果てはヌーヴェルヴァーグ映画への思い入れまでも注ぎ込んだコンセプチュアルなポップユニット。オールドファンにはポップスを消費しているように見えるらしく、かなり風当たりが強い。狂おしいほどの愛情も伝わらない時は伝わらないもんだ。
かなりのBeach Boysフリークとして知られる彼らだが、ボーカリスト野宮真貴の声質に合わないためか、表面的な影響は意外と少ない。彼らの楽曲でBeach Boysを感じさせるのは、野宮が加入する前のアルバム「on Her Majesty's Requiest」での高浪敬太郎作品。また、96年の企画アルバム「sister FREEDOM tapes」では、「Passing By」をカズーで演奏している。

Original Love

そのPizzicato Fiveのボーカリストだった田島貴男のソロプロジェクト。デビュー当時はソウルやジャズの影響を吸収した猥雑なサウンドで気取っていたが、だんだんと内省的なシンガーソングライタースタイルに移行していった。本人は今の方が素直でスピリチュアルだと思っていても、ファンは昔のスタイルを期待してしまうあたり、山下達郎的な存在と言える。
97年のアルバム「ELEVEN GRAFFITI」では、武川雅寛の軽妙なバイオリンが光る「SMiLE」テイストのインスト曲を発表している。フェイバリットナンバーは「Vegatables」だそう。

Chocolat & Akito

Great 3時代から、かたや音響派の音楽に近づきながら、かたや良質の王道ポップスを書いていた片寄明人。Great 3のデモ音源がまるで「Pet Sounds」で大笑い。そんな彼が奥さんのChocolatと作った2枚のアルバムは、アコースティックな手触りも感じられて、ソフトロックの見本市のような極めてハイクオリティーな作品。男女ボーカルのハーモニーがくすぐったい。Brianの来日ライブに御夫妻でいらしてました。

Springs

清く正しく美しく。今どき珍しい真っ当な胸キュンポップユニット。なんの屈託もない嬉し恥ずかしい詞世界も含めて、60年代のソフトロックを正しい形で再現している。Roger Nichols調、Phil Spector調、Fifth Dimension調といった定番ネタに混じってBeach Boysももちろんある。甘いストリングスをピリッと引き締める洗練されたコード進行、そして楽し気な男女のコーラスは、「Couples」期のPizzicato Fiveに匹敵するクオリティ。あとは歌詞が、ああ歌詞だけが惜しいのだ。
ボーカリストの違う1stアルバムもあるがこれは全く別物、ソフトロックファンには2ndアルバム「PICNIC」をお薦めしたい。

山下達郎
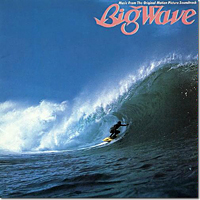
Doo Wopからソウルまで、アメリカのポピュラー音楽史を吸い尽くす達郎先生のポップスも、根っこにあるのはやっぱりBeach Boysだ。デビュー前の自主制作盤「Add Some Music To Your Day」は収録曲の半分以上がBeach Boysのカバー、以来1984年の企画アルバム「Big Wave」などで、しばしばBeach Boysナンバーを取りあげている。
残念なのは、日本のBeach Boysファンが達郎先生を中心としたムラ社会をなしていること。達郎先生がダメと言ったものはダメ、という風潮があるのは困った。達郎先生のポップス論には彼なりのこだわりが感じられるのだが、彼の意見を鵜呑みにするおじさん達の声からは若さへの嫉妬心しか伝わってこない。

大滝詠一

体系的なポップス博物学を下敷きにして、バリエーションとしてのポップソングをパズルのように組み立てる職人。もはやあっちの世界のものと思われるユーモアセンスと、驚異の柔軟性を持ち合わせていて、若手ミュージシャンからも絶大な支持を集めている。Brianと同じく、熱心なPhil Spectorマニアとしても有名。
Beach Boysの音楽も彼の頭の中ではパズルのピースとして存在しているらしく、「カナリア諸島にて」のサビに「Please Let Me Wonder」、「Fun×4」のエンディングに「Fun Fun Fun」、「禁煙音頭」のリフトコーラスに「Help Me Rhonda」を引用するなど、断片的な影響がそこここに見受けられる。そんな中で、サーフィンもののノベルティソング「泳げカナヅチ君」のコーラスアレンジは、珍しくストレートなBeach Boysへのオマージュになっている。

ヤン富田

元Water Melon Groupのスティールパン奏者。マッドサイエンティストにしてシャーマン。Sun Raを優雅なトロピカルサウンドに仕上げたかと思えば、街や野山でひろってきた環境音をコラージュしてみたりと、聴き手のポップス観を根底から覆してしまう音楽家だ。そもそも彼がスチールパンに目覚めたのはVan Dyke Parksの「Discover America」がきっかけだそうで、やっぱりその影にはBrianが見えてくる。
1995年にDoopees名義で発表したアルバム「Doopee Time」は、テープレコーダーが生んだ架空の女の子、Caroline Novakの心の成長を描くポップな1枚。となればアルバムのラストを飾るのは当然「Caroline, No」だ。彼らしいユーモアに包まれたアルバムの中で、透明な男声ボーカルと幻想的なヴィブラフォンが交錯する切ない演奏が引き立つ。
|